🎯はじめに:「真面目にやった子が損をする」クラス、つくっていませんか?
学校現場では、「きちんとやっている子ほど、待たされて損をする」という場面がよくあります。
例えばこんな場面、見覚えありませんか?
- ノートを真面目に書いていた子が、書き終わったあとずっと待たされている
- 帰りの支度を早く終えた子が、最後の子をじっと待つだけ
- 真面目に行動したのに、結局みんな同じように褒められる
こうした状態が続くと、子どもはこう感じ始めます。
「頑張っても、別にいいことないじゃん…」
これは、教師にとっても非常にもったいない状況です。
だからこそ、この記事では「早く終わった子が得をする仕組み」をつくる方法について、元教師の経験をもとにお伝えします。
🔍「早く終わった子」が損をする教室の3つの問題点
「やることをやった子ども」が報われないクラスには、以下のような問題点があります。
① 待たされるストレスが集中力を奪う
子どもは意外と繊細です。せっかく頑張って終えたのに、ただ待たされる時間が長いと、達成感どころかモヤモヤ感が残ります。
② 「やらなくても大丈夫」という雰囲気が広がる
真面目にやった子と、サボった子に同じ結果(報酬)が与えられると、クラスに緩んだ空気が流れます。
③ 教師が常に指示・声かけを続けなければならない
教師が「次は〜して」「早くして」と言い続ける構造では、クラスは自立しません。先生も疲弊していきます。
✅「早く終わった子が得をする」クラス運営の実践例
では、どんな工夫をすれば「きちんとやった子が得をするクラス」になるのでしょうか?
私が実際に行って効果があった事例を紹介します。
🕒1. ノートが終わった子から休み時間に!
ノート記入が終わった子から、席を立って遊びに行ってOKにするだけです。
ポイントは、「全員終わったら休憩」ではなく「個人差を認める」こと。
✅子どもたちは自然と集中してノートを書きます。
ダラダラと写す子が激減します。
🎒2. 帰りの支度ができた子から下校準備OK
給食袋を片づけて、荷物をまとめた子から座って読書や自由時間。
これだけで、教室の空気がピリッと引き締まります。
✅「時間内に動く力」が育ちます。
また「どうせ遅くてもいいや」と思っていた子も、周りの動きを見て焦るようになります。
🧩3. 活動の「進行状況」を見える化する
ホワイトボードに名前カードや番号マグネットで進行状況を可視化します。
例:
- ノート提出済みの子は「提出済」欄に名前を移動
- 帰りの支度完了で「帰り準備OK」ゾーンへ
こうすると競争ではなく、進行の見える安心感が得られます。
🌱やるべきことをやった子が報われると、教室がこう変わる
このような「得をする仕組み」をつくると、子どもたちは次のように変わります。
- ✅ 自分のペースで集中して取り組める
- ✅ 自分で行動を判断する力がつく
- ✅ 「早く終わらせて次に行こう」と前向きになる
つまり、ただの「ご褒美制度」ではなく、子どもの自立心や行動力を育てる本質的な仕組みとなるのです。
💡「得する仕組み」の導入で気をつけたい3つのこと
ただし、以下の点に注意しなければ逆効果になることもあります。
① ご褒美制度にならないように
あくまで「やるべきことをやった上での自由」であることを明確にします。
ただ早ければいい、ではなく「正確さ・丁寧さ」も評価の一部に入れると良いです。
② 遅い子への支援も同時に行う
支度が遅い子、集中が続かない子には、支援が必要です。
「置いていかれる感覚」を持たせない配慮も忘れずに。
③ 平等よりも「公平」を意識する
みんなに同じを求めるのではなく、「頑張りに応じて扱う」という公平な感覚を教師自身が大切にします。
📝まとめ:クラスが変わるのは、小さな仕組みから
「早く終わった子が得をする仕組み」は、特別な教材も時間もいりません。
✅ ノートが終わったら自由
✅ 支度ができたら帰る
✅ 自分で行動を判断する流れ
このような小さな仕組みの積み重ねが、クラス全体の空気を変えていきます。
そして、教師も毎回「まだ終わってない人〜!」と叫ばなくて済むようになります。
子どもの主体性を育てるのは、こうした日常の工夫から。
ぜひ、明日から1つ取り入れてみてくださいね😊
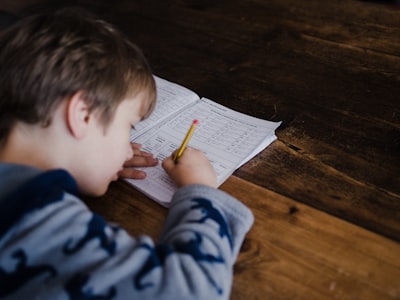


コメント